FP(ファイナンシャル・プランナー)2級、3級試験において、時間配分は試験対策として非常に重要です。
折角問題を正しく解いたのに、マークシートへの転記する際にズレている…
そんなことが無いようにしたいですね。
少しでもミスを減らす効率的に解答できる取り組みにどう対策すればいいでしょうか?
FP3級、FP2級、FP1級、AFP、CFP®のFP資格試験において全て合格した筆者が、それらの試験経験をもとに紹介します。
解答用紙に記載するタイミング
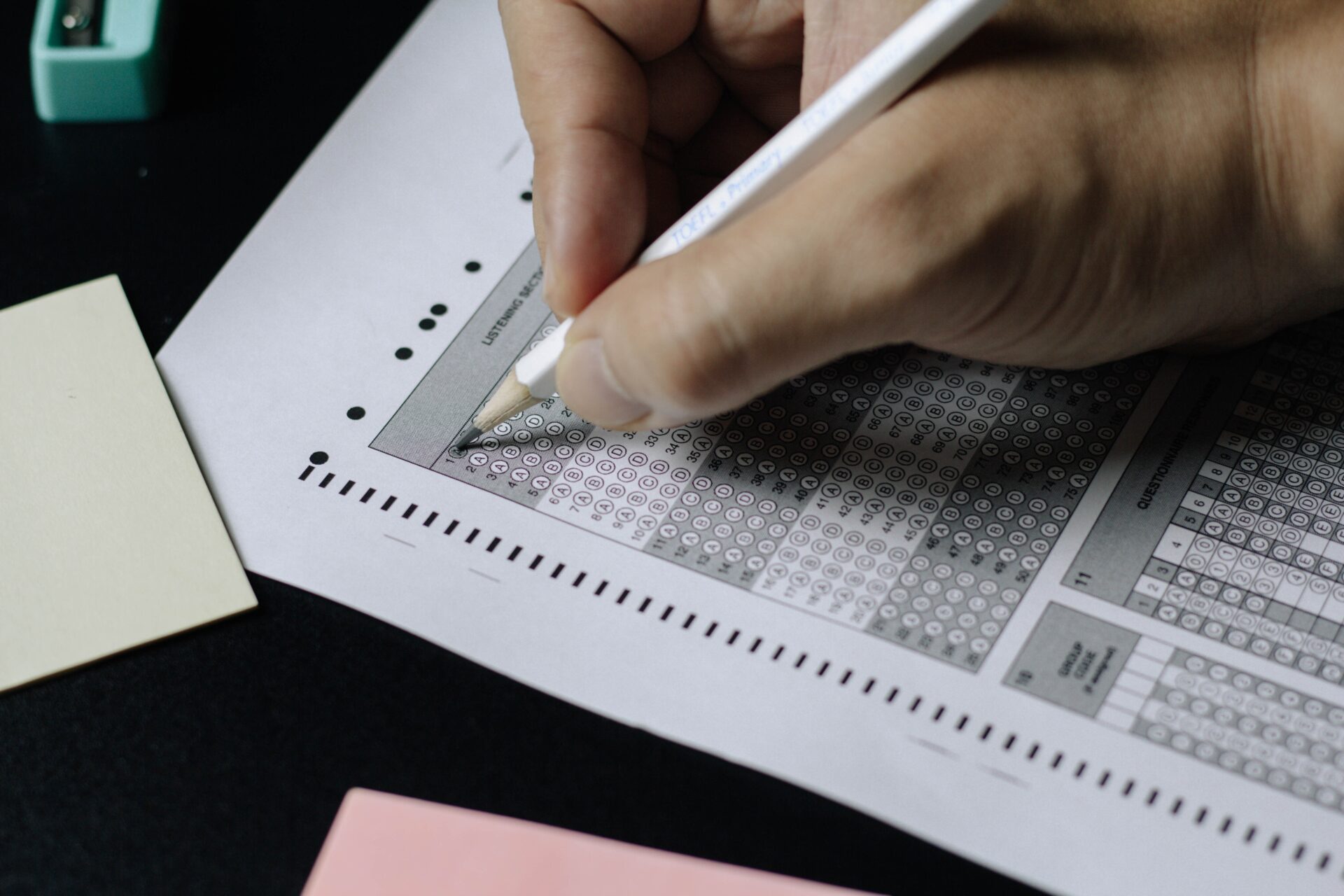
問題を解き終わった時に、いつ解答用紙に記載するのがいいのか考えてみます。
FPのようなマークシート方式試験は間違いがないよう、解答用紙にマークする必要があります。
これらを如何に効率的に、かつ早く終えるかが勝負です。
とにかく解答用紙に間違えないように転記するコツを見ていきます。
半分解き終わった時か全部解き終わった時か
筆者もFP全資格や、マンション管理士、宅地建物取引士等の数々のマークシート試験を受けてきて、解答用紙であるマークシートに転記するタイミングをいつにすればいいのかを良く考えます。
半分解答時と一括解答時に分けてみていきます。
半分解答のメリット
結論、時間配分がしっかりと出来ていればどちらでも良いような気はしています。
筆者の方法はほぼ一貫しておりました。
半分解き終わった時にマークシートに塗りつぶす「半分解答」です。
2回に分けてやることにより、解答時間が一時的に中断されるデメリットはあります。
一方のメリットとしては、
・2時間の試験の場合、1時間程度集中してきた頭をマークするという単純作業を間に入れることで一時的に休めて後半に臨むための切り替えが出来る
・まとめて全てマークする場合、後半の問題でつまずくと焦るため、半分解答しているという余裕が持てる
などが想定しうるところです。
そのメリットを享受するために、また「一括解答」のデメリットを避けるために、「半分解答」を実施しています。
一括解答のメリット
「一括解答」にもデメリットはあります。
時間ギリギリで全問解いた場合に転記の時間がほぼ無くなる場合です。
その場合、正しい解答が出来ないという試験上最大のデメリットは発生してしまいます。
メリットとしては、
・まとめてマークをするので、マークに集中することができる
などが挙げられるのではないでしょうか。
1問出来たら解答…は効率が悪い
当然ですが、問題を解き終わった度に、都度問題用紙とマークシートを行ったり来たりするほど効率が悪いものはありません。
正確にマークできるという最大のメリットはあります。
しかし時間の制約がある中の非効率さや集中力が都度途切れるなどデメリットがあります。
このデメリットが非常に大きく、あまり推奨できるものではありません。
ただこの方法は上述のことが感覚的に理解できるため、あまりいない気もします。
FP3級受験をする方でマークシートが久しぶりの試験であったり、初めての試験であったりすると、ついついやってしまいがちなので、注意が必要です。
見直しの時間を必ず設ける
「問題を解く」「解答をする」と並んで非常に重要な「見直しをする」ことでしょう。
この時間をしっかり確保できるか否かで試験の合否を左右すると言っても過言ではありません。
どのような考え方で見直しをすればいいのでしょうか?
試験10分前までには解答を終えるようにする

ほとんどの試験で、試験官が「終了10分前です。これからの退室は認めません。」ということを言うかと思います。
勿論、自分の時計を見ながらではありますが、これが一つの目安になるかと思います。
このタイミングまでに解答を終えておくとある程度余裕が出るでしょう。
ただ、自分にとって難しい内容であったり、問題を飛ばしていることもあります。
したがって、その段階でまだ解答が残っている場合があります。
試験までの逆算の勉強方法でも記載しました。
一方で、資格試験時間中であっても「試験中での逆算の思考」が非常に重要といえます。
具体的に、FP2級の学科試験の例を挙げます。
・しかしこのまま問題を解いてしまうとマークもできないし見直しもできない
・マークの時間と見直しの時間に最後の10分を確保する
・110分の試験で60問を解かなければならないと考える必要がある
・その場合は、110分÷60問=1.83分≒1分48秒
すなわち、1問に2分掛けられないという試験戦略の方向性が出ます。
となると、必然的に
簡単な問題は30秒程度で解答、難易度が高い又は苦手な問題は後回しで時間を掛ける
事となります。
ただし掛けることが出来たとしても3分で、5分掛けると時間がひっ迫してきます。
そのような問題に出くわした場合の考え方は、また別途紹介します。
マークシートに塗る時は慎重に
マークシートミスをしたら台無しなので、非常に大事な論点になるかと思います。
筆者の知り合いでも、マークがズレていて不合格だったという方がいました。
非常に優秀な方で、合格間違いないとされていた方でした。
しかも年1回しかない難関国家資格でこれをやってしまったのです。
FPは年3回あるから…とはいうものの、それでも悔やみきれないものが残ります。
そんなことが無いようにしなければなりません。
そのため、ここは少し時間が掛かってもマークミスが無いように対処が必要でしょう。
丁寧に問題用紙とマークシートを行き来しなければなりません。
「半分解答」の場合も「一括解答」の場合も同様ですが、焦らないようにして、間違った番号をマークしない様、またズレないように最大の注意を払わなければなりません。
塗りつぶした後必ず解答用紙の見直しを

FP2級学科なら60か所、FP3級学科でも50か所を塗りつぶさなければなりません。
見直しにも時間が掛かるため、出来ればある程度の時間を残しておく必要があります。
解答用紙のマークミスがないかの見直しは最低2周、出来れば3周はしたい所です。
マークがしっかりなされていない場合は、正確にマークを行う必要があります。
またマークの修正等は意外と時間を要する作業ともいえるでしょう。
そのため、素早くかつ慎重にと相反する対応が求められます。
試験中における時間配分で大切なこと4選+α
試験時間における時間の配分はどのようにすればいいのでしょうか。
ここは試験慣れしないと難しい点もあるかもしれません。
具体的に筆者が受けてきた試験経験から、大切なことを紹介します。
「ペラペラ」の時間
問題に取り掛かる際に必須なこと3選でも記載した「ペラペラ」の時間についてです。
この時間はあたりを付けるだけなので、1-2分程度で終えることが望まれます。
試験に慣れていない場合は、中々この時間のイメージが出来ないかもしれないでしょう。
しかしながら、、試験戦略においては、全体感を把握して全体戦略を考え、各問題に取り組むという個別戦略が重要になります。
したがって、全体感を掴みながら気になる所をチェックすることになります。
解答の時間
「ペラペラ」の後、残り10分前迄を意識して解答をしていく形になるかと思います。
時間配分的には、FP2級、FP3級の学科の場合は2時間のうち、1時間45分~1時間50分程度は割きたいものです。
問題の内容によってはもう少し早く終えられ、見直しの時間の確保も可能かもしれません。
しかしながら、このぐらいの時間を解答に当てる事が出来れば、ある程度の余裕を持って終えられると考えられます。
場合によっては問題との相性が良く1時間半程度で解き終わる場合もあるかと思います。
その場合は見直しに時間を充分かけた方が良いでしょう。
マークの時間
マークの時間はさほど掛かるものではないですが、慎重に行う必要があります。
チェックしながらという観点では、FP2級の60か所、FP3級の50か所ともに、少なくとも5分程度は確保したい所です。
見直しの時間

見直しの時間は残った時間を最大限使うことになると考えられます。
「ペラペラ」の時間、マークの時間が限られた範囲内でやる事になるので、如何に解答時間を確保しつつ、速やかに解くかで、この見直しの時間が確保されると考えられます。
最低10分は欲しい所ですが、残り5分でやらないといけない場合も出てくるでしょう。
時間配分のまとめ
FP試験の時間配分としては以下の通りになります。
FP2級実技は1時間半、FP3級実技は1時間のため、それぞれ解答時間が短縮される形になるかと考えられます。
| ペラペラ | 1-2分程度 |
| 解答 | 1時間45分~1時間50分程度 |
| マーク | 5分程度 |
| 見直し | 残りの時間(5分~10分) |
まとめ
今回は問題を解いた後の解答用紙への記載や、時間配分を中心に記載しました。
慣れないと中々柔軟な現場対応が出来ないのも事実でしょう。
このブログを読んだだけではイメージ出来ないかもしれないですが、120分試験の不動産4資格、FP3級~FP1級までの各試験と、CFP®6課目の試験等のマークシート試験に取り組んで来て研究しているので、重要なポイントは詰まっていると考えています。
実は、まだ試験中の対策として注意すべき点がありますので、分からない問題や難易度の高い問題に出くわした場合の対処方法や、試験前に準備しておいたことがいい事、試験時の小ネタなど、解答に有効に機能するコツも別途紹介します。




コメント