「ファイナンシャル・プランナー(FP)になるには資格が必須なのか?」と疑問に思う方は少なくないでしょう。実は、FPになるために資格は必ずしも必要ありません。この事実を知っている人は意外と少ないかもしれませんね。
筆者もFPについて学び始めた頃は、「資格がないと名乗れないのでは?」と何度も調べたり、人に聞いたりしていました。かつての私と同じように、FPの資格事情に迷っている方のために、今回は以下の疑問にわかりやすくお答えします。
✅FP(ファイナンシャル・プランナー)に資格が不要な理由を知りたい
✅資格がなくてもFPを名乗って問題ないのか確認したい
✅資格を持つFPにはどのような特徴があるのか知りたい
このような疑問に答えます。
筆者は、FP3級から学習をスタートし、FP2級、AFPを経て、上位資格であるCFP🄬やFP1級を取得した経験があります。この記事では、資格を持たずに活動するFPと資格を持つFPの違いを詳しく解説します。
そして、FPを目指す方や資格に興味がある方に向けた実践的な情報を提供します。
この記事でわかること:FP資格の全貌

今回紹介する内容は、
✅資格なしでもFPを名乗れる理由を徹底解説
✅名称独占資格3選:肩書を名乗れる国家資格とは
マンション管理士
中小企業診断士
ファイナンシャル・プランニング技能士(1級・2級・3級)
✅資格を持つFPの特徴とそのメリット
から構成されています。
FP(ファイナンシャル・プランナー)に資格が不要な理由

FPの業務内容と資格の関係を紐解く
FP(ファイナンシャル・プランナー)の主な仕事は、個人の資産設計に関するコンサルティングです。具体的には、貯蓄計画の立案、保険の選び方、老後資金の準備など、個々のライフプランに合わせた提案を行います。この業務には、特別な法的規制が設けられていないため、誰でもアドバイスを提供できるのが大きな特徴です。
たとえば、保険会社や不動産会社に勤める場合、実務経験や営業スキルがあれば、資格がなくても顧客に対して十分な提案が可能です。つまり、FPとしての活動において、資格は必須条件ではないのです。
独占業務との境界線
ただし、FP業務に近い分野では注意が必要です。以下のような業務は、特定の資格がなければ行えません。✅法務に関するアドバイス:弁護士や司法書士
✅不動産の売買:宅地建物取引士
実務での現実
実際のところ、FPとして活動する人の中には、資格を持たずに経験や知識だけで顧客対応をしているケースが多々あります。たとえば、保険の提案や住宅ローンのプランニングなど、実践的なスキルがあれば、無資格でも十分に仕事が成り立つのです。ただし、顧客からの信頼を得るためには、実績や人柄が重要になります。
資格なしでもFPを名乗れる理由
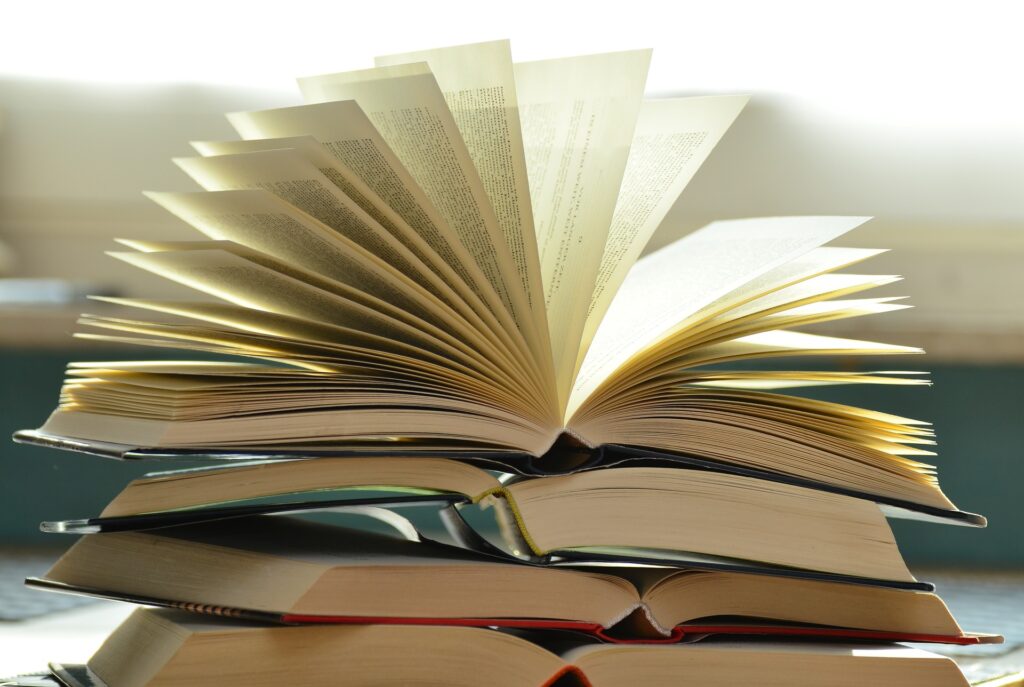
「ファイナンシャル・プランナー」は自由な肩書
意外に思うかもしれませんが、「FP(ファイナンシャル・プランナー)」という呼び方は、資格名ではなく自由に名乗れる肩書です。法律で規制されていないため、資格がなくても「私はFPです」と自己紹介しても何ら問題ありません。名刺やSNS、ウェブサイトでこの肩書を使っている人も少なくありません。
資格者と無資格者の違いを明確に
とはいえ、実務で活躍するFPの多くは、以下のような資格を取得しています。
✅民間資格:CFP🄬、AFP
これらの資格を持っていない場合でも、FPを名乗ること自体に法的制約はないのです。ただし、顧客や企業からの信頼を得るためには、資格が強力な後押しになることも事実です。
見分け方のポイント
✅「ファイナンシャル・プランナー」とだけ記載されている場合:資格を持っていない可能性があります
✅具体的な資格名(例:FP2級、CFP🄬)が記載されている場合:国家資格または民間資格の取得者
名刺やプロフィールをチェックすれば、その人が資格者かどうかをある程度判断できます。
名乗るだけなら簡単、でも信頼が鍵
資格なしでFPを名乗るのは簡単ですが、実際に顧客から依頼を受けるには、実績やスキルが求められます。資格がない場合でも、実務経験や知識をアピールできれば、活躍の場は広がります。たとえば、保険営業の経験がある人は、無資格でも顧客に信頼されることが多いです。
肩書を名乗れる名称独占資格3選
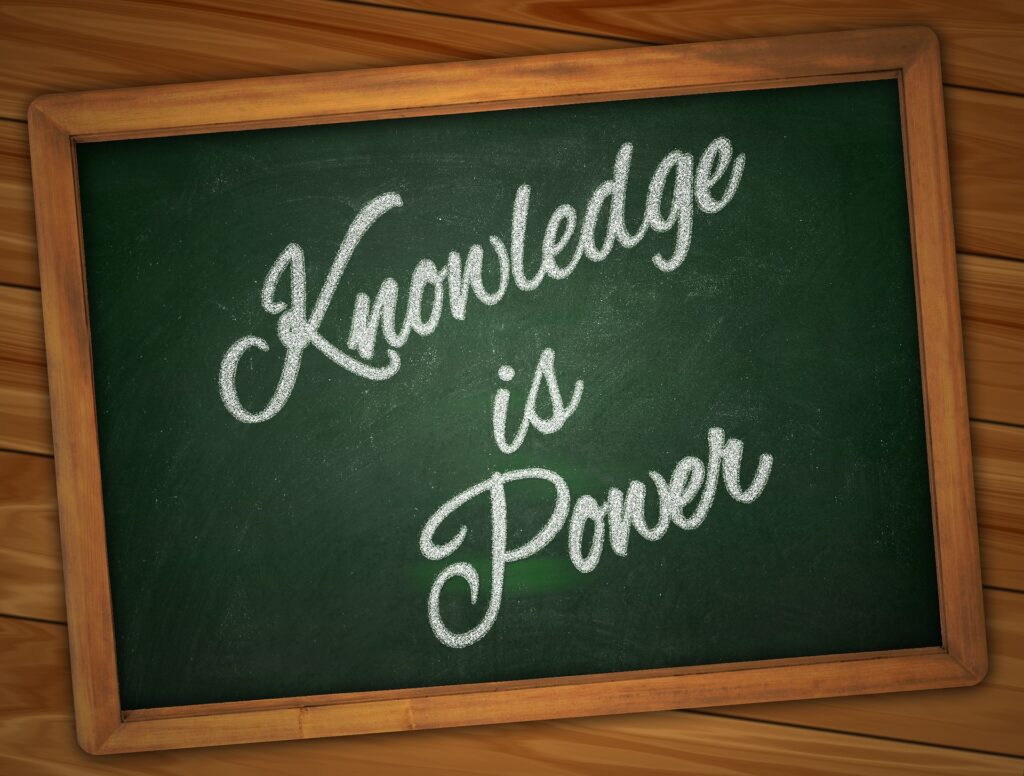
マンション管理士
まず、筆者も取得して活動しているマンション管理士についてです。
概要
マンション管理士試験を実施している、マンション管理センターの説明を引用します。
特徴
✅名称独占の典型例:資格がなくても業務は可能だが、肩書は資格者に限定されます
✅最近の動向:一部自治体では、管理計画認定書類の提出に資格が必要なケースも出てきました
独占業務は限定的ですが、信頼性の高い肩書として認知されています。
実務での活用
筆者もマンション管理士を取得し、管理組合のサポートに活かしています。最近では、自治体関連の業務で資格が求められる場面も増えており、名称独占資格としての価値が少しずつ高まっている印象です。
中小企業診断士
代表的な名称独占資格である、中小企業診断士についても見ておきます。
概要
中小企業診断協会の説明を引用します。
中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるに当たり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度です。
特徴
✅名称の使用:登録すれば「中小企業診断士」を名乗れます
✅実務での活躍:商工会議所や自治体の相談窓口で活躍するケースも多いです
明確な独占業務はないものの、実践的な場面で重宝される資格です。
歴史と現状
中小企業診断士は歴史が長く、知名度も高い資格です。たとえば、コロナ融資の認証業務など、自治体関連の仕事で窓口を担うこともあり、一定の業務範囲が確立されています。私が知る中小企業診断士は、経営相談で高い評価を受けていました。
ファイナンシャル・プランニング技能士
そして、ファイナンシャル・プランニング技能士です。
筆者は省略してFPやファイナンシャルプランナーとして記載したりしています。
本来FP2級は
「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」
と記載しなければなりません。
概要
同じく、FP1級、2級、3級についてです。
当ブログではお馴染みのFP試験団体でもある日本FP協会から引用します。
FP技能検定には、1級、2級、3級の等級があり、それぞれに学科試験と実技試験が設けられています。
学科試験と実技試験は同日に実施され、両方の試験を受検可能です。
日本FP協会の学科試験は2級、3級のみで1級の実施はなく、実技試験の科目は1級、2級、3級いずれも「資産設計提案業務」となっています。
学科試験と実技試験、両方に合格すると合格証書が発行され、等級ごとに「ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗ることができます。
また、学科試験もしくは実技試験のいずれかに合格すると一部合格証(兼結果通知)が発行され、「合格した試験実施日の翌々年度末」までに限り、次回以降に合格している試験を免除できます。
こちらも明確に、
等級ごとにファイナンシャル・プランニング技能士と名乗ることができる
と記載があり、名称独占資格であることが分かります。
特徴
✅名称独占資格:級ごとに肩書が認められます
✅試験内容:学科と実技の両方に合格する必要があります
現時点で独占業務はありませんが、知識の証明として多くのFPが活用しています。
試験の仕組み
日本FP協会によると、学科と実技は同日に実施され、両方に合格すると資格が取得できます。一部合格の場合は、次回以降に免除が適用される仕組みもあり、段階的にステップアップが可能です。私もFP3級から始め、徐々に上位資格を取得しました。
資格を持つFPの特徴とメリット

FP資格を持っているFPは、知識の裏付けとしてその業務を活かすために大半は名刺やホームページの自己紹介に、資格取得していることを記載されているでしょう。
ファイナンシャル・プランニング技能士ならびに、AFP、CFP®それぞれのFP資格者の特徴を簡単に紹介します。
国家資格:ファイナンシャル・プランニング技能士
✅FP2級:一般的な知識を備えた中級者向け。名刺に記載する人も多いです
✅FP1級:高度な知識と実務経験を持つ上級者向け。専門性の証となります
これらは職業能力開発促進法に基づく国家資格で、信頼性の裏付けとして機能します。
民間資格:AFP・CFP🄬
✅CFP🄬:FP1級と同等の上位資格。30単位の継続教育が求められます
AFP・CFP🄬の厳格さ
資格取得の具体的なメリット
✅知識の証明:専門性を明確にアピールできます
✅キャリアアップ:独立や転職で有利になります
資格がないFPと比較すると、見え方的にも明確な差がつくのは間違いありません。たとえば、名刺に「CFP🄬」と記載するだけで、初対面の顧客からの反応が良くなることがあります。
FP資格の取得方法とステップ
FP3級からのスタート
FP資格の入門として、FP3級がおすすめです。試験は学科と実技に分かれており、基礎的な知識を学ぶのに最適です。勉強時間は約50~100時間程度で、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。
FP2級へのステップアップ
FP3級に合格したら、次はFP2級を目指しましょう。こちらは実務で通用するレベルの知識が求められ、勉強時間は約150~200時間程度。実技試験では具体的なケーススタディが出題されるため、実践的な視点が身につきます。
AFPやCFP🄬への挑戦
FP2級を取得したら、AFPやCFP🄬に挑戦するのも良い選択肢です。AFPはFP2級合格後に研修を受けることで取得でき、CFP🄬はさらに難易度の高い試験に合格する必要があります。私もこのルートでステップアップしました。
学習方法の選び方
✅独学:テキストと過去問で学ぶ。コストを抑えたい人向け
✅通信講座:体系的なカリキュラムで効率的に学習したい人向け
✅スクール:講師の指導を受けたい人向け
私は通信講座を活用し、効率的に資格を取得しました。
FP資格を活かしたキャリアパスの具体例
企業内FPとして活躍
保険会社や銀行では、FP資格を持つ社員が顧客対応を行うケースが増えています。FP2級以上があれば、昇進や部署異動で有利になることもあるでしょう。
独立系FPとして開業
資格を武器に独立する人も多いです。とりわけ、FP1級やCFP🄬といった、上位FP資格を保有していれば、経験を積むことによって、独立開業の可能性も出てくるでしょう。
教育や執筆活動
FP資格を活かして、セミナー講師や執筆活動を行う人もいます。私もブログや記事執筆を通じて、FPの知識を広める活動を楽しんでいます。
よくある質問とその回答
Q1.FP資格なしで仕事はできる?
A:はい、できます。資格がなくてもFPを名乗り、業務を行うことは可能です。ただし、信頼を得るためには実績やスキルが重要です。
Q2.どの資格から始めるべき?
A:初心者ならFP3級がおすすめ。実務を目指すならFP2級やAFPを視野に入れましょう。
Q3.CFP®は難しすぎる?
A:難易度は高いですが、段階的に学習すれば十分取得可能です。私もFP3級から始めて、1年ちょっとで達成しました。
まとめ:FP資格は不要でも、あると有利!

FP(ファイナンシャル・プランナー)になるために資格は必須ではありません。誰でもFPを名乗り、業務を行うことができます。しかし、資格を持つFPは知識と信頼性の裏付けがあり、顧客に選ばれやすいのも事実です。
まずはFP2級やAFPを目指すことから始めてみてはいかがでしょうか。キャリアの第一歩として、確実に成果につながるはずです。以下のリンクも参考に、FP資格の取得を検討してみてください!
FP資格取得のメリットと資格の活かし方(きっと成果に繋がる)
テキスト紹介
通信講座紹介
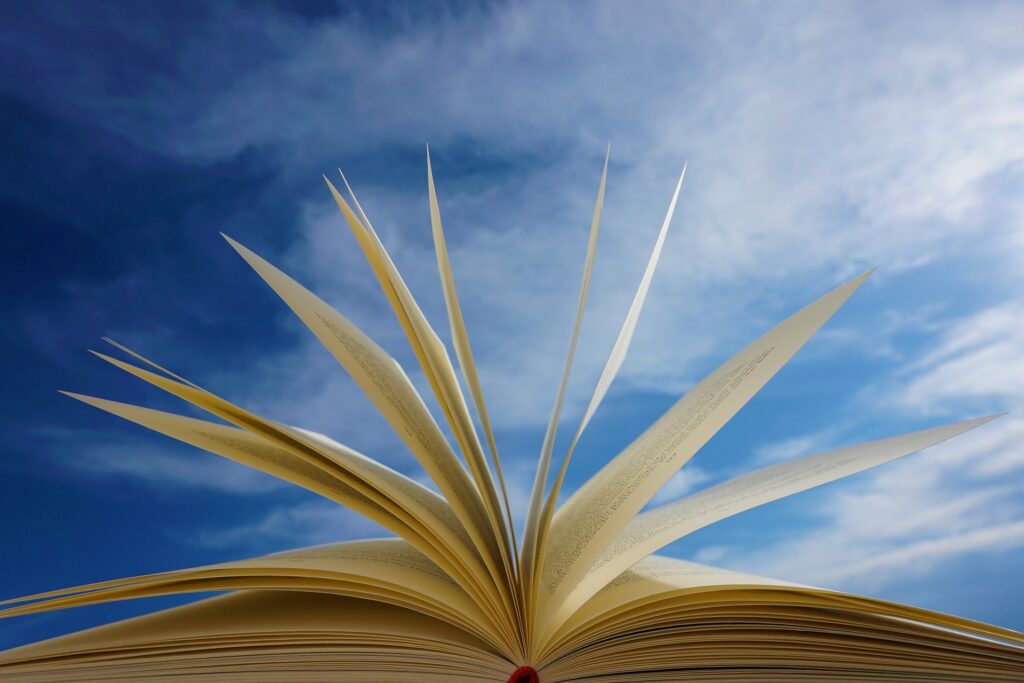






コメント