FP(ファイナンシャルプランナー)2級に難易度って、受験をする方や受験を検討している方にとっては、勉強量や時間の確保の観点からも気になる所かと思います。
実際に、どの資格と似たイメージをもっておけばいいのでしょうか。
一方で、得意、不得意があるので単純比較は難しいと思います。
今回、FP3級~FP1級まで順次受験し、AFP、CFP®にも合格した筆者が、一定の目安として今回紹介したいと思います。
難易度の比較について
まず、難易度を比較するにあたり、一般的に言われている
業務上の必要性や、経験者が受験する資格であるなどの定性的な特性
を一部加味してみてみます。
また、筆者が資格取得したものも含まれるため、実績値も一部加味しました。
ただし、あくまでも全てにおいて当てはまるわけではないこと、また筆者の独自判断に基づくものである点について、予めご了承ください。
FP2級合格のための学習時間
FP2級と他の資格との難易度の比較については、単純には難しい所はあります。
しかしながら、
・ある程度覚悟して臨まなければならない資格なのか
自分や周囲が持っている資格と比較をするうえでの目安となります。
FP2級の学習時間についてはこちら
でもご紹介したとおり、150~300時間です。
・FP業務をなされている方
・金融や不動産業にお勤めの方
は150時間かそれ以下の比較的短時間でも取得可能でしょう。
一方で、
・FP3級を取得したものの暫く時間が空いてしまった方
などは、300時間が必要になってくるかもしれません。
また、難易度が近かったり科目上近い資格として、
・証券外務員2種
・簿記2級と3級
・宅地建物取引士
とともに確認していきたいと思います。
FP2級の合格率の確認
そして、基準となるFP2級の合格率についても確認しておきます。
FP2級はFP協会の試験ですが、こちらの記事
からですが、学科試験は40~55%で推移しており、
対して実技試験は50~70%で推移しています。
さらに、実技×学科のいわゆるストレート合格率になると20%~37%
と年によって振れ幅はありますが、比較するうえでの一定の基準値となりそうです。
賃貸不動産経営管理士(賃管)との比較

まずは、2021年試験から国家資格化となり、受験者とともに難易度も急上昇した賃貸不動産経営管理士からみてみます。
資格の概要や合格率は?
※一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 ホームページより
合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者合格率 |
| 2013年 | 4,106 | 3,946 | 3,386 | 85.80% |
| 2014年 | 4,367 | 4,188 | 3,219 | 76.86% |
| 2015年 | 5,118 | 4,908 | 2,679 | 54.58% |
| 2016年 | 13,862 | 13,149 | 7,350 | 55.89% |
| 2017年 | 17,532 | 16,624 | 8,033 | 48.32% |
| 2018年 | 19,654 | 18,488 | 9,379 | 50.73% |
| 2019年 | 25,032 | 23,605 | 8,698 | 36.80% |
| 2020年 | 29,591 | 27,338 | 8146 | 29.50% |
| 2021年 | 35,553 | 32,459 | 10,240 | 31.50% |
| 2022年 | 35,026 | 31,687 | 8,774 | 27.70% |
| 2023年 | 31,547 | 28,299 | 7,894 | 27.90% |
※2020年から40問→50問となっており、2021年から国家資格となっています。
賃貸不動産経営管理士資格の傾向は?
2021年から国家資格化し、その前兆である2019年から急に合格率が低下しており、2022年は合格率が27.7%と過去最低になりました。
また、
賃貸不動産経営管理士の学習時間は100~200時間
ののようであり、こちらもおおむねFP2級と被っています。
ただし、国家資格化したうえ、不動産業界で宅建などの他資格からの追加で取得する方も想定されるため、今後の推移等みていく必要はありそうです。
さらに、合格率と時間の観点からになりますが、
FP2級と賃貸不動産経営管理士の難易度はほぼ同じ
ではと考えられます。
二種外務員(証券外務員2種)との比較
次に、証券資格である、二種外務員について、確認していきます。
二種外務員資格の概要
証券外務員2種は、日本証券業協会の説明によると、
(注)店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・複雑な投資信託、レバレッジ投資信託、株式の信用取引、新株予約権証券、有価証券関連デリバティブ取引等に係る外務員の職務は行えない。
また、外務員とは、協会員の役員又は従業員のうち、その協会員のために、金融商品の販売・勧誘等を行える者。
とあります。
これは、一定の条件のもとで金融商品の販売や勧誘を行うことができる者という位置づけの資格者となります。
二種外務員資格の合格率
さらに、合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 3,870 | 2,573 | 66.5% |
| 2019年 | 3,131 | 2,042 | 65.2% |
| 2020年 | 2,725 | 1,878 | 68.9% |
| 2021年 | 2,846 | 2,006 | 70.5% |
| 2022年 | 2,413 | 1,700 | 70.5% |
また、外務員は、取得しなければ金融商品を販売することができない、
いわゆる独占業務ができる資格
であるため、受験生はそれなりに準備をして臨むことが想定されます。
学習時間は数十~100時間程度のようです。
こちらも、ある程度実務経験を兼ね備えている方が多いと想定され、時間を割かなくてもクリアできるものである点が挙げられそうです。
さらに、FP2級に対して、合格率も高く学習時間も比較的短いようです。
受験者層の違いにより、比較対象として難しい所もありますが、
数値から見る限りではFP2級の方が難しいのでは
と想定されます。
簿記2級、簿記3級との比較
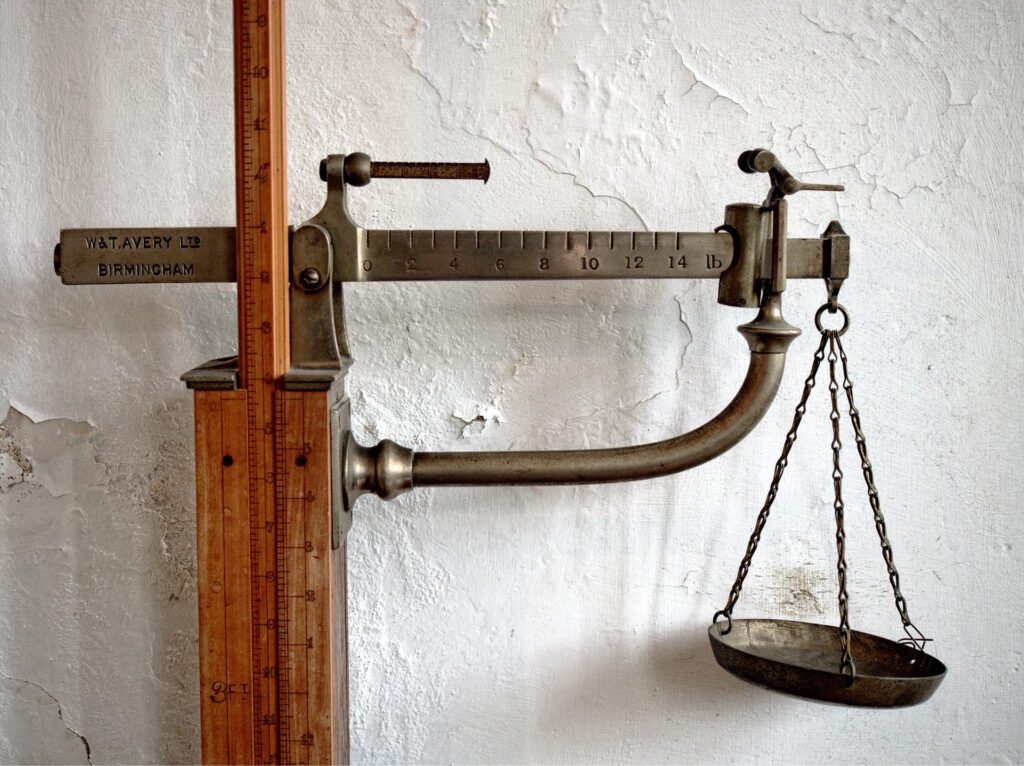
資格取得の中でFPと並んで人気資格上位にくる簿記についても見ていきます。
簿記2級と簿記3級それぞれの受験レベルは?
まずは、簿記2級についてです。
とあります。
さらに、簿記3級は、
とあります。
簿記2級と簿記3級の合格率の推移は?
そして、簿記2級ならびに、3級の合格率の推移をみていきます。
簿記2級の推移
<簿記2級 統一試験>
| 回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 165(2023.11.19) | 11,572 | 9,511 | 1,133 | 11.9% |
| 164(2023.6.11) | 10,618 | 8,454 | 1,788 | 21.1% |
| 163(2023.2.26) | 15,103 | 12,033 | 2,983 | 24.8% |
| 162(2022.11.20) | 19,141 | 15,570 | 3,257 | 20.9% |
| 161(2022.6.12) | 16,856 | 13,118 | 3,524 | 26.9% |
| 160(2022.2.27) | 21,974 | 17,448 | 3,057 | 17.5% |
| 159(2021.11.21) | 27,854 | 22,626 | 6,932 | 30.6% |
| 158(2021.6.13) | 28,572 | 22,711 | 5,440 | 24.0% |
| 157(2021.2.28) | 45,173 | 35,898 | 3,091 | 8.6% |
| 156(2020.11.15) | 51,727 | 39,830 | 7,255 | 18.2% |
| 155(2020.6.14) | 中止 | |||
| 154(2020.2.23) | 63,981 | 46,939 | 13,409 | 28.60% |
| 153(2019.11.17) | 62,206 | 48,744 | 13,195 | 27.10% |
| 152(2019.6.9) | 55,702 | 41,995 | 10,666 | 25.40% |
簿記3級の推移
<簿記3級 統一試験>
| 回 | 申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 165(2023.11.19) | 30,387 | 25,727 | 8,653 | 33.6% |
| 164(2023.6.11) | 31,818 | 26,757 | 9,107 | 34.0% |
| 163(2023.2.26) | 37,493 | 31,556 | 11,516 | 36.5% |
| 162(2022.11.20) | 39,055 | 32,422 | 9,786 | 30.2% |
| 161(2022.6.12) | 43,723 | 36,654 | 16,770 | 45.8% |
| 160(2022.2.27) | 52,649 | 44,218 | 22,512 | 50.9% |
| 159(2021.11.21) | 58,025 | 49,095 | 13,296 | 27.1% |
| 158(2021.6.13) | 58,070 | 49,313 | 14,252 | 28.9% |
| 157(2021.2.28) | 70,748 | 59,747 | 40,129 | 67.2% |
| 156(2020.11.15) | 77,064 | 64,655 | 30,654 | 47.4% |
| 155(2020.6.14) | 中止 | |||
| 154(2020.2.23) | 100,690 | 76,896 | 37,744 | 49.10% |
| 153(2019.11.17) | 99,820 | 80,130 | 34,519 | 43.10% |
| 152(2019.6.9) | 91,662 | 72,435 | 40,624 | 56.10% |
簿記2級と簿記3級の合格率の傾向は?
過去10回における2級の合格率は20%程度、3級は40%程度で推移しており、双方とも難化傾向です。
また合格のための学習時間は、簿記2級で250~500時間、簿記3級で数十~100時間程度と言われています。
簿記2級に幅があるのは、3級学習経験者だと2~300時間、未経験の場合は300~500時間掛かると言われており、それなりの覚悟をして臨まないと合格できない資格であると言えそうです。
従って、合格率と学習時間の難易度の順で行くと、難しい順より、簿記2級>FP2級>簿記3級に位置づけられそうです。
宅地建物取引士(宅建)との比較
最後に、FPと比較的親和性がある宅地建物取引士(宅建)との比較をしてみます。
簿記やFPと並んで、非常に人気が高い独占業務を持つ資格として有名ですね。
宅地建物取引士の資格概要と合格率
そして、合格率の推移です。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2014年 | 238,343 | 192,029 | 33,670 | 17.50% |
| 2015年 | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.40% |
| 2016年 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.40% |
| 2017年 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.60% |
| 2018年 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.60% |
| 2019年 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.00% |
| 2020年10月 | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.60% |
| 2020年12月 | 55,121 | 35,258 | 4,609 | 13.10% |
| 2021年10月 | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.90% |
| 2021年12月 | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.60% |
| 2022年 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.04% |
| 2023年 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.16% |
上記より、平均合格率は約16%です。
また、宅建はFPと違い相対合格試験で、合格通知がくるまでは合格か不合格か分かりません。
宅地建物取引士の学習時間や難易度は?
過去の学習経験や不動産経験の程度にもよりますが、宅建合格のための学習時間は300~500時間と言われています。
筆者は2回受験していて、初年度は400時間、2年目はマンション管理士と賃貸不動産経営管理士受験の年に宅建に100時間割きましたので、おおむね近い値ではないでしょうか。
このことから、合格率や学習時間を考えると、
難易度的には宅建の方がFP2級に比べて難しい
といえます。
各資格との比較まとめ
そして、時間と合格率を基準とした難易度になります。
一覧にして整理しておきます。
| 資格試験 | 平均合格率 | 学習時間 | FP2級との難易度の比較 |
| FP2級(学科と実技ストレートで合格の場合) | 約28% | 150~300時間 | – |
| 賃貸不動産経営管理士 |
約31% | 100~200時間 | ほぼ同じ |
| 証券外務員二種 |
約68% | 数十~100時間 | 優しい |
| 簿記2級 | 約20% | 300~500時間 | 難しい |
| 簿記3級 | 約40% | 数十~100時間 | 優しい |
| 宅建 |
約16% | 300~500時間 | 難しい |
※平均合格率は各資格で紹介した数値の平均値を取っています
※FP2級は日本FP協会主催の2018年9月試験から2023年9月試験の間における学科平均合格率(46.93%)×実技平均合格率(59.25%)で算出しています
STUDYINGの通信講座にはそれぞれの講座が開設されており、タブレット学習法とも親和性があります。
とりわけ、択一式問題が中心である不動産系資格は、FP資格の勉強方法と親和性があるので、タブレット学習がお勧めです。
まとめ

今回は、FP2級と学習範囲が近い資格試験について挙げてみました。
ご紹介したこれらの資格は、筆者も取得しているものが複数あり、ともに取得することで更にスキルとしてパワーを発揮すると考えられます。
FP2級×他資格の観点でスキルアップの参考になれば幸いです。






コメント