FP(ファイナンシャルプランナー)試験において、電卓(計算機)は持ち物として必須です。
※FP3級は2024年からCBT試験に移行し電卓持ち込みは無くなりました
※FP2級も2025年からCBT試験に移行予定です
もちろん受験生にとって、試験前までに使い慣れて臨むことがほどんどでしょう。
・お勧めの電卓
ついても、触れていきます。
電卓の使いこなし次第で、計算のスピード感も格段に違ってきますので、
賢く使いこなしたいですよね。
FP試験における電卓については、前日の準備編
でも少し触れていますので、参考にしてみてください。
FP試験において電卓を賢く使いこなす4つのポイント

無意識に家にある電卓を使い始めた、ということで利用し始めることが比較的多いと思います。
試験時間中は常に電卓を手放せない状態ですが、あるコツを踏まえておくと
比較的スムーズにいくことがあります。
今回筆者のFP試験や簿記試験等、電卓を使用する資格試験の経験も含めて、
賢く使いこなす4つのポイントにまとめてみましたので紹介します。
試験までに電卓に使い慣れること
これはいわば当たり前の話になりますが、試験直前に電卓を買い替えることは厳禁でしょう。
一から使い方に慣れなければならない可能性があります。
故障した場合等やむを得ない場合は、
同じ型のものを買うか、少なくとも同じメーカーのものを買う
ことをお勧めします。
メーカーについては次に記載します。
メーカーを揃えた方がいい

一定のメーカーを揃えた方がいい理由は、一部例外はありますが、
「キーの並びが同じであること」です。
これは、実は違ったメーカーの計算機を複数使っていると、
計算している際に何気なく手間取ってしまう原因となり、場合によっては計算間違いにも繋がってしまいます。
メーカーを統一することにより、配列を指に覚えさせることも可能になります。
実は非常に大事なポイントで、やむを得ない場合を除いては、
試験前に複数揃えておくことが望ましいでしょう。
安すぎる電卓は辞めた方がいい
他の記事を見ていると「予備で100均の電卓を準備しておくと…」という記載がありますが、これも予備用の一つの手段としてはあるかと思います。
しかしながら、100均の電卓とメーカーの電卓、どちらが試験日において安定感が増して不安が無くなるかは明らかでしょう。
キーが小さすぎて打ちずらい、ボタンが押しずらいなどもあると考えられます。
筆者としては、後述するように、忘れた場合などのどうしようもない場合は止むを得ないかと思いますが、安めの電卓は何があるか分からないことを想定して辞めた方がいいと思っています。
利き手のことを考える?
筆者はこれまで意識したことはなかったのですが、右手で書く人は左手で電卓が打てるようになる、またその逆が出来るようになると効率が上がると聞いたり見たりしたことはあります。
確かに、訓練でこれが出来るようになると相当な効率化に寄与すると思います。
筆者は右で書きますが、ペンを持ちながら右で叩いたり、簡単な計算なら左で叩いたりと双方で利用しますが、パターンを固めた方が効率的かもしれません。
FP試験の会場に持ち込む電卓に関する注意点

試験会場に持ち込む電卓に関して、どのような点に注意をすればいいのでしょうか。
筆者が試験に臨んだ経験から、気になった点を中心に紹介します。
FP協会の試験要綱より電卓を使用する際の注意事項
FP協会の試験要綱には、電卓(計算機)について、以下の様な注意があります。
イ.電源内蔵のもの(そろばん不可)
ロ.演算機能のみを有するもの
※使用可………√・%・定数計算、消費税に係る税込・税抜、売上に係る原価(MD)・売上・売価(MU)・利益率、日数・時間計算、マルチ換算についてのキー、メモリー(M)機能(計算結果を 1 つだけ記録できるものに限る)、GT キーのあるもの
※使用不可……関数機能(∑(シグマ)・log 等)・ローン計算・複利計算・紙に記録する機能、音(タッチ音・音階・音声等)を発する機能、プログラム(計算式)の入力(登録)機能、計算過程を遡って確認できる機能等を有するもの
ハ. 数値を表示する部分がおおむね水平で、文字表示領域が1行であるもの
ニ . 外形寸法がおおむね 26㎝ × 18㎝の大きさを超えないもの
2) 計算機は故障に備えて複数台持込みできますが、試験中に使用できるのは 1 台のみです。使用する計算機以外はカバン等にしまってください。
※試験中の計算機の交換は試験監督の許可が必要です。
3)試験会場での計算機の貸出しは行いません。
電卓の予備は必ず準備する
前項の3)にあるとおり、忘れても貸して貰えません。
また予備も無い場合は
計算問題は暗算や筆記で解かなければならない
という最悪の事態になります。
これは電卓を利用する資格試験の鉄則ですが、結果的になんともなかったとしても、通常用と予備用の2台持っていくのは必須でしょう。
あまり電卓が壊れたというのは聞いたことが無いですが、急いでキーを叩いてしまって、通常とは違うモードに切り替わってしまって、動きがおかしくなった…といったことは非常に多く発生します。
そのような場合でも、試験官に対して
「電卓の調子が悪いので、変えさせてください」
といって許可を貰って取り換えることができますし、むしろ時間が掛かるようならお勧めします。
合格の為には、あらゆる手段を使って乗り切るのが資格試験の鉄則と言えるでしょう。
電卓を万が一忘れたらコンビニかスーパーへ急げ
これは絶対になくしたい失敗ですが、万が一電卓を忘れたらコンビニかスーパーへ急ぐこととなるでしょう。
もちろん、開始直前に気づいてしまったら、万事休すというところですが、必ず前日や当日の朝、持ち物チェックはしたいものです。
買いに行く場合、試験会場は比較的人が集まる所であるため、近隣にお店がある可能性があります。
持ち物の確認は前日と当日の朝に徹底的にやらなければならないですが、朝勉強していて、そのまま計算機を鞄に入れずに来てしまったという、最悪パターンは避けなければなりません。
少なくとも、
・電卓
は絶対に持って試験会場へ行くことです。
受験票はなくても当日再発行は可能ですし、時計も無くても何とか乗り切れますが、筆記用具と電卓は貸してくれず、忘れてしまうとどうしようも無いので、絶対に忘れないという点は徹底した方がいいでしょう。
ちなみに、試験要綱にある当日の携帯品です。
2) 本人確認書類(詳細は「12.本人確認書類」参照)
3) 筆記用具(HB の鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム)
4) 計算機(詳細は「13. 計算機」参照)
5)腕時計 ※音の出るもの、通信機能を有するものは不可。
※筆記用具・計算機・時計の会場での貸出しは行いません。
メーカー別電卓の違い
メーカー別でどのような違いがあるのか、キーの並びと複利計算の例を取り上げて比較してみます。
電卓キーの並びの違い
特に配列に決まりがないようで、メーカーによってキーの並びが違っています。
目で見て覚えるより、手が感覚的に動くようになっていると、これもまた気になる視点かもしれません。
特に簿記など、電卓をフル活用しなければならない秒を争う試験は、電卓に使い慣れていないとちょっとしたことでロスになってりします。
FP2級はそこまでではないかもしれないですが、CASIO,SHARP,CANONのそれぞれのメーカー別の並びを見てみましょう。
各社比較してみると、結構特徴が出ていて面白いです。
CASIO
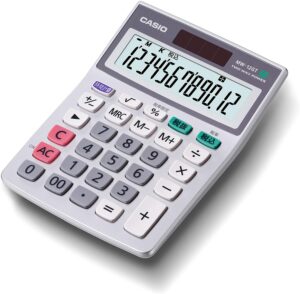
筆者が愛用しているのはCASIO製です。
多用するACキー(オールクリアキー)とCキー(クリアキー)が左側にあるのが特徴で、これに慣れてしまっています。
さらに、0が一番右側に、00がその内側にあるのも特徴的で、=が・の横にあります。
あと、÷×-+が右に並んでおり、ここも昔も今も変わらない配列です。
SHARP
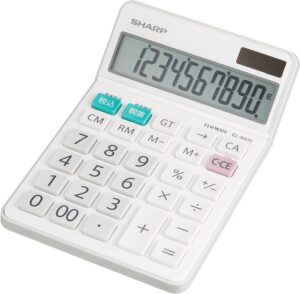
数字の配列は変わらないのですが、正方形の中にまとまった形になっています。
CASIOと比べ+と=が逆転しているのと、C(クリアキー)とCE(クリアエントリーキー)が同じキーになっています。
ちなみにCはメモリー以外を全てクリアし、CEは表示数値のみクリアとなります。
SHARPホームページ「[C]キーと、[CE]キーや[CA]キーとの違いは何ですか?」より
CANON

このならびもまた2社と違い、個性的です。
CASIO同様、CとCA(オールクリアキー)が外側にあり、数字が四角形に配置されており、÷×-+=も四角形に配置されています。
ただCANONでも配置がちょっと違うものもあるようですね。
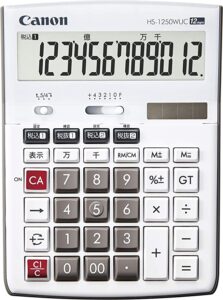
CとCAやTAXの位置が違ったりしています。
電卓で実施する複利計算の例より
例えば良く出て来る、100万円を10年間毎年1%の複利で運用した場合の10年後の運用額を計算してみます。
1.01××1,000,000==========(=を10回押す)1,104,622.…
・SHARP・CANONの場合
1.01×1,000,000==========1,104,622.…
になります。
CASIOはおーちゃん【1級FP技能士】TVに「単利と複利の電卓の叩き方#46 FP3級2級左右分割骨太講座」にも分かりやすく紹介動画があります。
こういう時短に寄与するテクニックは必ず頭に入れておきたいものですね。
筆者お勧めの電卓3選
最後に、筆者がお勧めする電卓を、12桁対応のものを中心に3つ紹介します。
CASIO MW-12GT-N
筆者も愛用しているベストセラーのCASIO MW-12GT-N です。
比較的軽くて、持ち運びにも便利、また1000円台前半で購入することが出来る安さなど、FP試験攻略では色々なところで紹介されています。
筆者も試験勉強でこれを購入し、引き続き業務等においても今はこれをメインで使用しています。
リーズナブルであり、コンパクトで重宝する1台かと思います。
SHARP EL-VN82-NX
何故か電卓50周年の記念モデルがベストセラーになっており、SHARP好きの方にはこちら欲しいってなるような電卓です。
見た感じもお洒落なので、女性向けという感じな気がしています。
CANON HS-1250WUC
商売計算対応実務電卓という副題がついている、抗菌仕様の12桁電卓です。
CANON製は先にも触れましたが、キーがメーカー内でも統一ではなく、様々な種類のものがあるようですね。
まとめ
電卓について紹介しましたが、筆者も記事を書いていて、これだけ電卓に対して確認したことはなかったので、想定外の発見もありました。
電卓は普段使い慣れたものを、そのまま試験会場に持っていくのが一番良いでしょう。
また、忘れずに予備電卓も準備して臨んで頂ければと思います。




コメント