FP通信講座はタブレット学習法と非常に親和性があります。
テキストやノートをタブレット化出来れば、持ち運びにも非常に便利であるため、
スマホ+タブレットだけで、どこでも勉強が可能です。
そして、実際にはどのような方法を取ればいいのでしょうか。
今回は筆者が活用して合格してきた方法とともに4つのポイントに分けて紹介したいと思います。
タブレット学習法と通信講座の相性がいい理由
筆者のタブレット学習法は、「スマホ+タブレット」で学習する方法であり、
紙のテキストは原則考えていないパターンです。
特にスタディングはどれもデータのみで完結する講座になっているので、
非常に相性がいい通信講座です。
もちろん紙のテキストや問題集の併用でも十分に力を発揮します。
アガルートアカデミーやフォーサイト等の通信講座の中には、
授業はオンラインで実施するけど、テキストは紙というパターンもあります。
そこにも順応できるような方法を今回は取り上げたいと思います。
授業がタブレットやスマホで受けられる
この点はすぐに思いつく点であるかと思いますが、授業がスマートフォンもしくは、
タブレットで受講することが出来ます。
スタディングやアガルートアカデミー、フォーサイト
の講義は基本的に双方に対応しているので、
通勤時や外出時、昼休みなど、あらゆるパターンで利用することが出来、
隙間時間で学習できるという有効活用が可能です。
そして、これが通信教育の一番のメリットでしょう。
PDF化されたテキストや問題集との相性がいい
もしテキストがPDF化やデータ化出来る場合、GoodNotes等の専用のノートアプリの連携することにより、紙のテキストの持ち運びが不要となります。
以下、筆者が効率的な勉強方法として連続して試験に合格してきた、
データ版の活用方法を紹介しています。


通信講座はこのようなデジタル化との親和性が非常に高くなっています。
仮にテキストを紙のままで活用するにしても、ノートはタブレットを使用すると、
持ち運びにも非常に便利で、またスマホとも共有したりすることも可能です。
追記がしやすい
ノートやテキストにタブレットに入っているアプリを用いて使用する場合、
追記が非常にしやすくなります。
書いたり消したりが非常に楽な事と、関連する事項を追記したい場合において、
ノートのスペースが無くなっても、簡単に新たなページを追加することが出来るためです。
通信講座の学習方法

先に少し触れましたが、講義をどのような形で見るかにより、学習のしやすさも変わります。
また、自宅や外などの勉強する場所によっても変わるでしょう。
それぞれのケースにおける学習方法について考えてみたいと思います。
自宅学習はPCとの相性が良い
自宅にPCがある場合には、自宅学習はPCとの相性が良いと考えられます。
理由はやはりモニターの存在で、授業が大きめの画面で見ることが出来る点でしょう。
さらに手元にタブレットやノートを置くスペースも比較的確保できることもあります。
外出時、特にカフェなどでの学習は中々この環境が構築できない点もあります。
そして、PCに限らずですが、
講義の板書で気になるところはスクリーンショットを取って保存
ができます。
ノートがタブレットであると、
スクリーンショットの画像をタブレットのノートアプリに貼り付け
が出来て、その上から自分のコメント等書くことも可能でしょう。
外出時はスマホ+タブレットで
タブレット学習法においては、外出時はスマートフォンとタブレットが手軽でお勧めです。
これは重いテキストを持っていく必要がない点で利点です。
しかしながら、やむを得ず紙のテキストを使用する場合は、プラス紙のテキストか、
タブレットの代わりに紙のノートという場合もあり得るでしょう。
テキストを横に置き講義をスマホで見てノートに転記する、そんな形になります。
特に旅に出る時やワーケーションを行う場合には、学習テキストやノートにおける、
すべてのデータ化により、持ち運びには大変重宝します。
勿論、通学が出来ないため、独学を除くとアガルートアカデミーやフォーサイトといった
通信講座は必須になると考えられます。
スマホのみでも可能

繰り返し講義を聴くだけでしたら、通勤中や外出中にスマホだけでも可能でしょう。
ただし、スマホで講義をただ見る場合は、「インプット」中心の学習になり、
あくまでもノートに書いたりできない場合でしょう。
インプットは勉強効率としては学習初期の段階は必要です。
しかしながら、インプット一巡後は過去問演習を中心としたアウトプットが適しており、
スマホを使った一問一答や選択問題などのアウトプット重視が望ましいと言えます。
タブレットをテキストやノートとして使う場合のメリット
タブレットをテキストやノートとして使うメリットは、
筆者が合格した各試験でそのコツを享受しているので、非常に有効的だと考えています。
具体的には以下のメリットが挙げられます。
自分流オリジナルテキストが可能
ベースのテキストは通信でも電子書籍でも購入できますが、
仮にPDF化、画像化などによりタブレットのノートアプリとの連携が図れるなら、
そこに自分の苦手な箇所をどんどん書き込むことが出来る自分流のオリジナルテキスト
を作成することができます。
紙のテキストでも勿論書き込んで作成することは出来ますが、
多くのノートアプリには文字検索機能が付いているため、
ある程度雑な字体であっても、どこに何を書いたか瞬時に検索することが可能です。
これがタブレット学習法の利点の一つでもあります。
仮に紙のノートなら、どこに何を書いたか暫く目視で探さないといけないうえ、
消したりする場合も、後が残ったり紙が破れたりなど、結構面倒な目に合う可能性もあります。
その心配が全くいらないのが、タブレットのノート化ということかと思います。
スマホに取り込んだりプリントアウトしたりできる
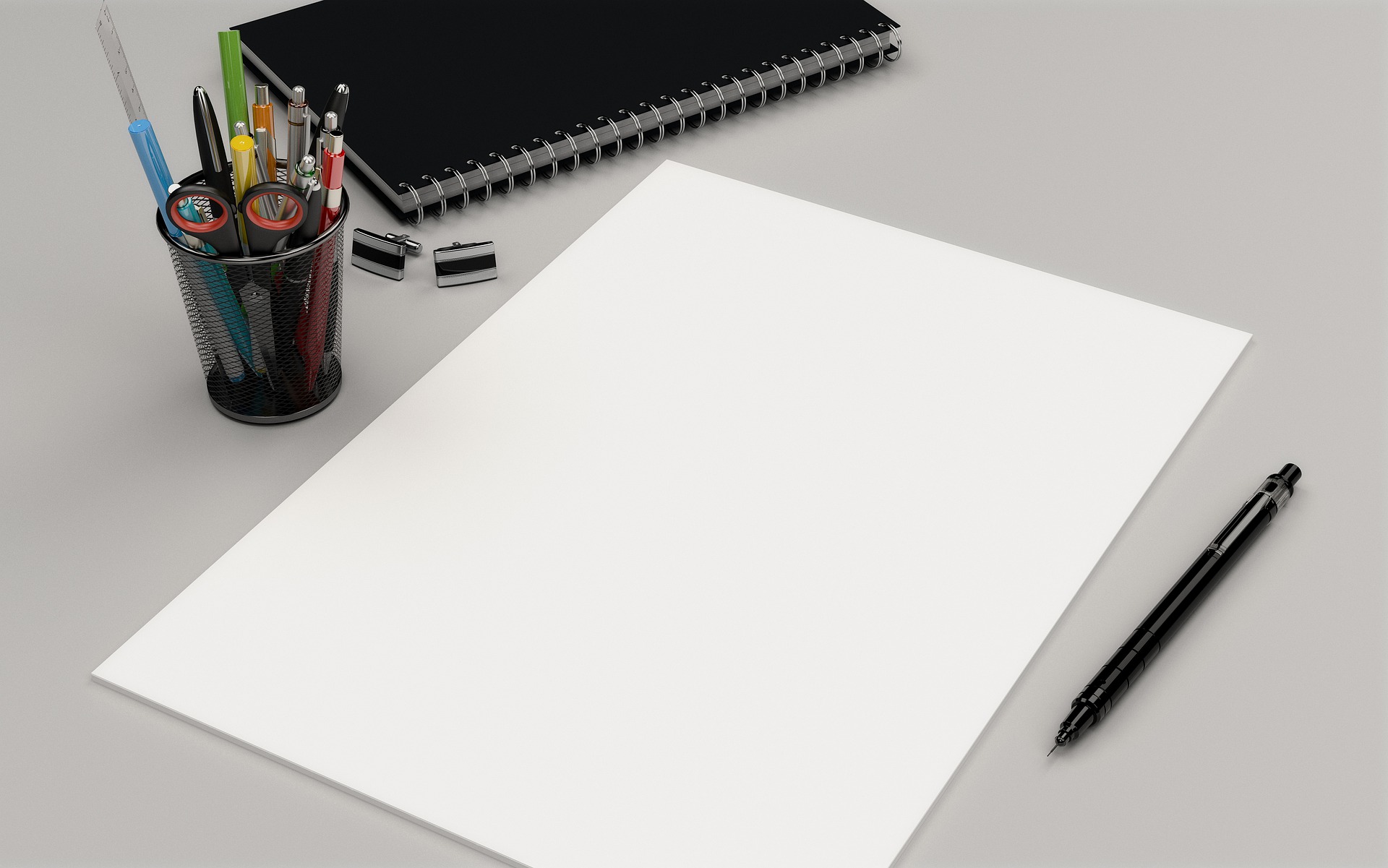
自分のオリジナルテキストは、
テキスト全体や選択部分をPDF化してスマホに取り込むことも可能です。
iCloudやGoogle Driveを介して、データを簡単に取り込むこともできるでしょう。
また直接タブレットとスマホのアプリ連携で、そのまま閲覧も可能になります。
この便利さは一度使うと手放せないので、早く使い慣れて効率的な学習に進めていくことを何よりもお勧めします。
これだけでも紙で学習しているライバルとの差は歴然で、効率化による短期間での合格も目指すことが可能です。
通信講座+タブレット学習法における確認事項
通信講座をタブレット学習法で行う場合には、どのような点に注意しておけばいいのでしょうか。
最後にまとめてみたいと思います。
タブレットは自分に合ったサイズを選ぶ
タブレット学習法にお勧めのタブレット
として、サイズ感を記載しています。
使いやすさ⇔持ち運び
がトレードオフになりがちですが、自分に丁度合うサイズを選ぶことが適切です。
筆者はFP3級、FP2級、CFP®6科目を通じてiPad10.2インチで攻略してきましたが、選択肢が多いFP3級、FP2級は違和感なく使えました。
ただCFP®は、筆者の場合はタブレットに取り込むよう6教科全ての教材をデータ化しました。
特にリスクと保険科目は読み込ませることにより、複数ページに渡る事が多い為、行ったり来たりでややタブレットは苦労しましたが、電子データと紙データの効率を考えると、やはり慣れている電子データでの勉強が良かったと思っています。
動画はデータ量を消費するのでWi-Fi環境が望ましい

講義の動画はデータ容量を消費するので、通信環境を考える必要があります。
カフェなど無料Wi-Fiがある環境下で学習する分にはいいかと思いますが、それ以外の通勤中や外出中に見る場合は、通信容量の消費が非常に大きくなる点に注意が必要です。
持ち運ぶ場合は、講座によっては音声がダウンロードできる場合もあるので、そのような対応をしてから受講することも要検討です。
ノートアプリはタブレットに対応しているものをダウンロード
iPadや、Android系のタブレットなどにより、アプリの対応状況が異なってくる場合があります。
筆者が普段使いで使用しているGoodNotes5はApple系のアプリのみになっています。
購入したタブレットに対応しているノートアプリをダウンロードする必要がありますが、それぞれ使い勝手や評判等で判断することになるかと思います。
iPadでしたらGoodNotes5がオススメですが、その他標準のノートアプリでも活用することが出来ます。
改めてこちら
をご参照ください。
通信講座のテキストのノートアプリへの取り込み方法を確認する
特にマイノートやテキストがデータ化されているスタディングは筆者の攻略法であるタブレット学習法と最も親和性があります。
また、アガルートアカデミーやフォーサイト
の講座は紙のテキストですが、工夫すればノートアプリとの連携も可能です。
具体的には、苦手な箇所だけを写真を撮って取り込んで読み込んだり、講義の板書をスクリーンショットとして取り込み、ノートアプリに貼り付けてオリジナルノートを構築するなどはすぐにできます。
また、筆者が実施してきたことで一番の効率化の源泉は、自己の利用の範囲内でテキストを自炊してデータ化することです。
※著作権上、紙のデータは処分されることが一般的です
※参考リンク
まだまだPDF化している教材が少ないのも事実ですが、工夫することでタブレット活用による効率化も考えられます。
まとめ
通信講座とタブレット学習法で親和性が取れる所を中心に紹介しました。
テキストは紙であっても、ノートはタブレットで電子化することで、講義の板書も上手く取り込むことが出来たり、自分流に加筆したりして理解の促進がより図れます。
通信講座と連携して、より効率的なタブレットを用いた学習を考えてみるのも、合格への近道かもしれません。
今回紹介した講座は以下
からも確認できます。
とりわけ、FP合格率において非常に高い合格率を誇るアガルートアカデミーには私もテキストでお世話になったおーちゃん先生の分かりやすい講義があります。
語呂合わせもお世話になり、今でも覚えていて使っているぐらいなので、実務でも重宝するでしょう。
各講座、講師・講座の特徴により、受験生の学習スタイルに合う合わないがありますので、比較しながら確認されるのが宜しいかと思います。



コメント